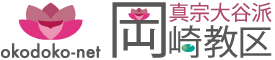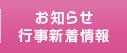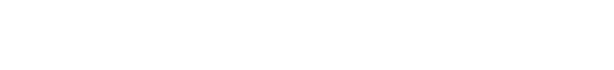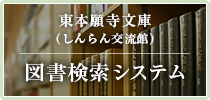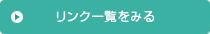岡崎教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法会
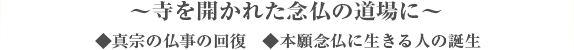
「何故、今、寺なのか」
このたびの、御遠忌法会は教区教化委員を中心とした「御遠忌法会実行委員会」が計画を推進しています。この『御遠忌通信』では、その取り組みを皆様と共有していけるよう、計画内容を随時掲載してまいります。今回は、実行委員会を代表して渡邉晃純氏より、御遠忌法会に向けての課題提起をいただきました。
「岡崎教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法会」を
スタートとして《何故、今、寺なのか》
岡崎教区宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法会実行委員会
本部 渡邉 晃純
「ところで、こうして、突如として斑鳩の里に出現した、いわば異端の、この瓦葺きの中国式宮殿について、ここで、いちばんに強調しておきたいことは、いま異端という言葉をことさらに用いたように、おそらく、当代の上代宮殿の造営にとっては、タブー(禁忌)であったに相違ない瓦葺の宮殿建築が、斑鳩の地にのみこうして出現していたという点である。当代にあっては、瓦葺といえば、直ちに、寺院建築を意味していた(中略)
瓦葺という宮殿のつくりの変革もさることながら、いやこの変革と深く関わり合っていることではあるが、ここで習俗上の問題として見落とされてならないのは、この斑鳩宮は、推古天皇30年(622)に、厩戸(うまやど)と、その妃膳菩岐々美郎女(かしわでのほききみのいらつめ)とが一日違いで相継いで薨(こう)じたあとも、なお、それを忌みもせずに、引続き、山背大兄王(やましろのおおえのおう)ら上宮王家の人びとによって住み継がれている点である。先代が死ぬと、一代限りで宮殿を遷すという、当時の風俗上の大原則が、ここでは全く顧みられていない。それと言うのも、上宮王家の人びとにとっては、死というものが、穢れとして、忌みきらわれ、おそれられてはいないからである。死にたいする観念というものが、まったく違ったものになってきているからである。それは、仏教思想の浸透が、王家の人びとの日常生活にまでふかくおよんでいたことを物語っている。」
(『斑鳩の白い道の上に』上原 和著P200~P203抄出 朝日新聞社 刊)
あらためて、確かめれば、瓦葺きか板葺きかは信仰上の問題であり、単なる習俗上の、また建築材料の問題ではなかったのである。それは、上宮王家の人々にとっては、死というものが、穢れとして、忌みきらわれ、怖れられてはいないからであったからであり、死というものにたいする観念が、全く違ったものになってきているからである。
寺は、人間が死に打ち克(か)った勝利の徴(しるし)であったのである。
仏教では時代を下ると末法と呼ぶが、これは進歩史観という呼び方が常識である今日では、いぶかしく思われる人が多いと思う。しかし、どうだろうか。一体、何をもって人間は進歩したと呼び習わしてきたのだろうか。『仏説阿弥陀経』には、有名な五濁の語があり、これが末法の具体的相と言われている。濁とはにごりであり、それは存在の曖昧さを指すと教えられている。生きているにもかかわらず、生きていることの証が感じられなくなったこと、と。
進歩が物質の豊かさによって量られ、物質の豊かさは、経済成長、つまり数値に置き換えられ、絶えず右肩上がりの数値によってのみ、評価されている。
その結果、年間3万人超の自死、夥しい数の鬱病患者などなどを産み出してきている。人間のための経済成長であったがはずが、経済成長のために人間が存在するという逆転が起こってしまった。これが、「にごり」といわれる状況といえようか。
「あなたにとって 幸福とは 何ですか。呼吸が 出来ることです」と応えた水木 しげるさん。生きることと、幸せが直結している、いわば、生きていることと幸せが別ではない、いきていることが、生き甲斐であるような、そういう人生を見つけられる眼を、育てることこそが、生きることであるということに思いをはせることが出来なくなった、それが果たして進歩なのか。つまり、進歩こそは末法(退歩を伴っている)と仏教では人間の歩みに警告を発信してきたのだろう。
今、岡崎教区では、上に挙げたような問題意識を持ちつつ、「寺を開かれた念仏の道場に」と課題を、「寺」と言うところに集約して、今後の歩みを始めようとしている。
それは、寺が現代の市民(地域)から、どれだけその存在について、対話出来る存在と言われるような情報を発信できているかと思うからである。一つは「和国の教主聖徳王」(親鸞聖人作)の和讃からも教えられるように、聖徳太子を「日本に出られた釈尊」と尊ばれたのは何故だろうか。「人間とは その知恵ゆえに まことに 深い闇を生きている」(高 史明)と言われた、その知恵こそを自己(主体)として何の疑問も持たない者を、聖徳太子は凡夫と言い当ててくださった。つまり、主体・真実の自己として疑うこともなくしている、その自我をこそ、人間の迷いの当体であると見いだしたのが、仏教であった。実は自我と言われてきているものを「虚仮」とみいだしたのが、法然上人の師である、善導大師でもあった。(『観経』至誠心釈)
「進歩の実態」は、成ってみれば全てを当たり前としてしか考えず、例えば、エネルギーの消費について考えるならば、一体どれだけ消費すれば、我々はもうそれで十分と言えるのか、「あたりまえ」の前には、「もっと、もっと」であり、欠乏感のみが残り、充足感はおこりようがないからである。
「すなわち、近代人は自分の欲することを知っているというまぼろしのもとに生きているが、実際には欲すると予想されるものを欲しているにすぎない。(略)
ひとが、本当になにを欲しているかを知るのは、多くのひとの考えるほど容易なことではないこと、それは人間がだれでも解決しなければならないもっとも困難な問題の一つであることを理解することが必要である。」
(E・フロム『自由からの逃走』P278抄出東京創元社刊1993年3月101版)
このフロムの提起、「ひとが本当になにを欲しているかを知るのは多くのひとの考えるほど容易なことではない」と言う提言の前に立ち止まる人がどれだけいるであろうか。
この「ひとが本当になにを欲してかを知るのは容易なことではない」という指摘に端的に応えられているのが、次の文であろう。
「称名はよく衆生一切の無明を破し、よく衆生一切の志願を満てたもう」(『教行信証』「行巻」真宗聖典p161)とあるように、生きていることが、生き甲斐であるような、「幸福とは呼吸のできること」と、言いうる質を持った生へと限りなく転じていく、生活の質を獲得していくこと、それが、この世に、少なくとも、親鸞聖人により明らかにされた仏道の根拠地としての寺が発信し続けている情報、つまり、「ただ念仏の救い」であったに違いない。
清沢満之の「自己とは何ぞや。これ人世の根本的問題なり」とは、あなたは何を持って、自己としていますかという確かめである、といえよう。